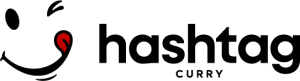「カレーって、いつから日本の味になったんだろう?」
そんな素朴な疑問から始まった今回の旅。出張先の食堂で何気なく注文したカレーライスが、想像以上に奥深いストーリーを語りかけてきたのです。そう、日本人とカレーの関係は、ただの“人気メニュー”という枠をはるかに超えていました。
カレーの日本上陸は、海の向こうから
日本にカレーが伝わったのは、明治時代初期のこと。
西洋の影響を受けて近代化をか、イギリス経由で“インド風の煮込み料理”としてカレーがやってきました。ただし当初のカレーはスパイシーさよりもシチューに近く、日本人の口に合うようアレンジされたものでした。
その立役者こそ、日本海軍。
海軍カレーが育てた「習慣としてのカレー」
海上での長期航海において、曜日感覚を保つために“金曜日はカレーの日”という慣習が生まれました。これは、栄養バランスの取れた一皿としても理にかなっていたそうです。
この海軍の“カレー文化”がやがて家庭に広まり、学校給食にも波及。
気がつけば、「毎週食べる習慣のある料理」として、カレーが日本人の生活に深く根付いていったのです。
戦後、カレーは「家庭料理」の主役へ
戦後、ルウタイプの即席カレーが登場したことも大きな転機でした。
調理の手間が減り、子どもから大人まで幅広く愛される味。昭和の食卓では「今夜はカレー!」というと、家族みんながわくわくする——そんな定番の一品になったのです。
そして、外食文化の中でも独自の進化を遂げ、「カツカレー」や「スープカレー」、「スパイスカレー」など多様なスタイルが登場。いまや日本のカレーは、世界にも類を見ない独自のカルチャーを築き上げまし。
カレーは“日常”であり“冒険”でもある
旅をするたびに感じるのは、どこに行ってもカレーはあるということ。
老舗の洋食屋で食べるクラシックな欧風カレーも、スパイスの香りが炸裂する南インド風も、どれも“日本のカレー”として受け入れられているのが面白い。
そしてそれが、日本人の柔軟な味覚と文化の懐の深さを表しているように思えてなりません。
まとめ:なぜ、カレーは国民食になったのか?
- 異文化を受け入れる懐の深さ
- 海軍から学校・家庭への普及
- 手軽さと味の自由度
- 進化し続ける多様性
こうして振り返ってみると、カレーが国民食になった理由は、ただ「美味しい」からではなく、時代とともに変化し、私たちの暮らしにそっと寄り添ってきたからなのかもしれません。
次にカレーを食べるとき、ほんの少しその背景に思いを馳せてみてください。
一皿のカレーの中に、じつは日本の近代史がスパイスのように溶け込んでいるかもしれませんよ。