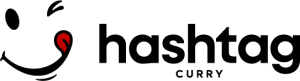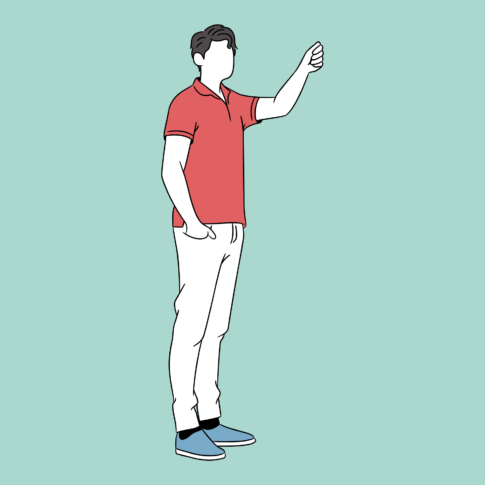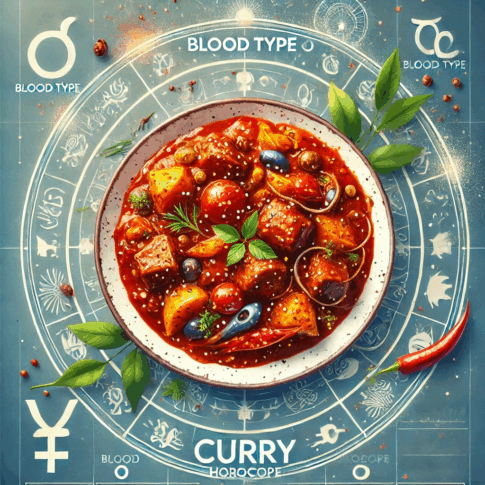インドやネパールのカレーを食べたことがある人なら気づくと思います。
本場のカレーは、ターリー(インドの定食皿)やミールス(南インド式の定食)のように、カレーが小鉢に分けられ、ライスやナンと一緒に少しずつ混ぜながら楽しむのが一般的です。
では、なぜ日本のカレーは「ご飯とルーを一緒の皿に盛る」スタイルになったのでしょうか?
背景にあるのは“西洋料理”の影響
カレーが日本に入ってきたのは明治時代。インドから直接ではなく、イギリス経由でした。
当時のイギリスでは、小麦粉を使った“カレー風味のシチュー”をライスにかけて食べるスタイルが主流。日本人にとっても「おかずとご飯が一度に食べられる便利な料理」として受け入れやすかったのです。
日本式の合理性と相性抜群
もうひとつの理由は、日本人がもともと「ご飯におかずをのせて一緒に食べる」文化を持っていたこと。
牛丼、親子丼、天丼…どんぶり文化に慣れていた日本人にとって、ライスにカレーをかけるスタイルは自然な選択でした。
さらに1皿にまとまるので 提供が早く、洗い物も少ない。学校給食や社食に広がるには、これ以上ない合理性でした。
“混ぜて食べる”楽しみを昇華
インドのようにカレーを別皿にせず、あえてライスにルーをかけたからこそ、日本のカレーには独自の楽しみが生まれました。
スプーンでひと口ごとに「ルー多め」「ライス多め」とバランスを調整しながら食べるのは、日本式カレーならではの体験です。
まとめ
日本のカレーが“1皿完結型”になった背景には、イギリスのカレーシチュー文化の影響、日本人が慣れ親しんでいたどんぶりの食文化、そして給食や家庭料理に広まりやすい合理性がありました。
その結果生まれたのが、インド風でも西洋風でもない、日本独自のカレー。ライスとルーを同じ皿に盛るという当たり前のスタイルには、実はそんな歴史と文化の融合が息づいているのです。